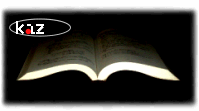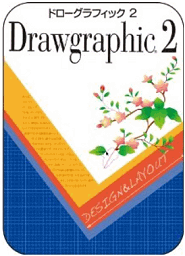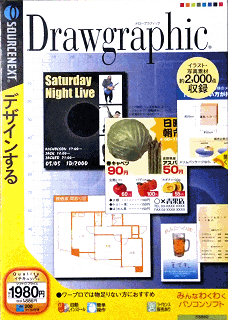|
■1■ 用紙サイズを設定する |
|
【ポイント】 用紙は新規作成か、デフォルトのA4用紙から変更する |
|
Drawgraphic 初期版 への挑戦記録は → こちらをクリック |
|
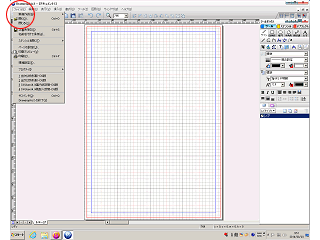 |
|
DG2 を開くと最初に表示される画面では、A4縦の用紙がデフォルト(=初期設定)されている。
これから作成する「街道案内資料」はA4横サイズだ。総17ページの作品だが、ここでは試みにその内の7ページ目を作成。
まず、用紙をA4横に変更する。
ファイル(F)
↓
ページの設定(U)
|
|
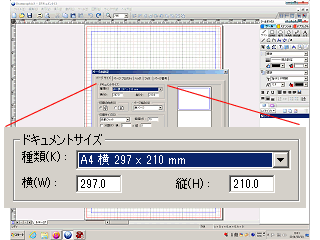 |
|
↓
[ページサイズ] タブをクリック
ドキュメントサイズの窓から、
A4 横 297 x 210 mm を選択
↓
[OK] ボタン
|
|
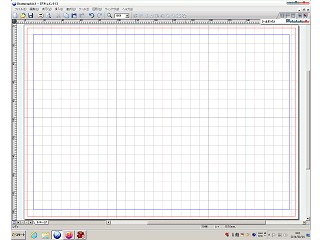 |
|
A4 横の用紙に変更した画面。
「ツールボックス」は上向きのボタン [∧] を押して隠してみた。これで、画面が広々と使える。
|
|
|
|
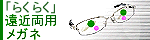 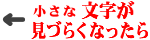 |
|
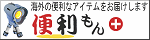 |
|
|
|
|
|
■2■ ガイドライン(仮想線)を設定する |
|
【ポイント】 ガイドは初期版よりも設定しやすくなった |
|
Drawgraphic 初期版 への挑戦記録は → こちらをクリック |
|
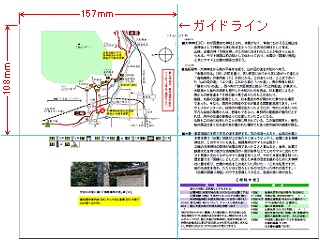 |
|
ようやく、作業に入る。
まずDTPの定番「ガイド」の設定だ。 左はここで作る資料の7ページ目のG.CREW での完成画面。G.CREWでは「ガイドライン」と呼び色はブルー。
これから貼り付ける画像(イラストや写真)と文章の位置の目印になる仮の線だ。 画面上では見えるが、印刷されないので「仮想線」とも呼ばれる。
左の例では縦横2本だが実際の作業では10数本引いている。 |
demo
|
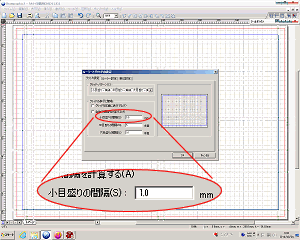 |
|
「ガイド」を設定しようとすると、近くの「グリッド」(= マス目)に吸い付く(= スナップする)。この作例では「ガイド」をmm単位で設定するので、予め次の手順で「グリッド」をmm単位に細かくしておく。
左上メニューバーの
ツール(T)
↓
ルーラーとグリッドの設定(E)
↓
グリッド設定で、「自動…」を外して「小目盛りの間隔」を「1.0mm」にする。
|
|
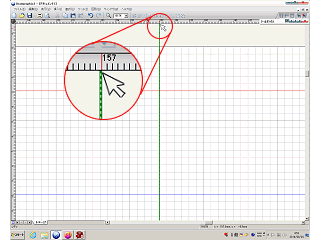 |
|
「ガイド」の色はグリーン。DG2 では設定方法が、初期版とは変わった。
縦ガイドの場合…初期版では左のルーラー(定規)からズルーと引き出したが、DG2 では、上のルーラーを拡大し、希望目盛にマウスポインターを合わせて下へ少し降ろせば、一発で「希望位置に」ガイドを配置することができる。
これは手早くて便利だが、mm数字による設定機能は引き続き見当たらない。 |
|
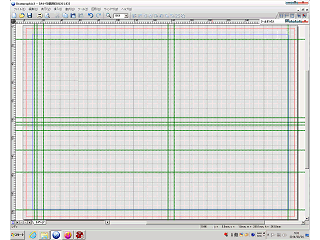 |
|
左はこのようにして、すべてのガイドを設定した画面。
ガイドは設定後にマウスが触れても動かないよう「ロック」しておこう。
左上メニューバーの
ツール(T)
↓
ガイドのロック(K)
保存ファイルを開く(= 呼び出す)と、毎回ロックは解除されるので注意!
|
|
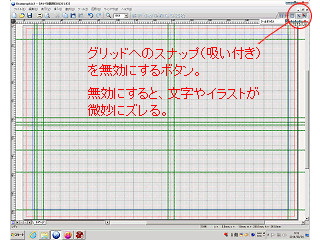 |
|
文字やイラストを配置すると、グリッドやガイドラインにスナップする。(吸い付く)。この機能で位置がそろってすっきりするが、場合によっては微妙な調整のじゃまになる。そんな時は「無効」にできる。
スナップの強さは、ツール(T)→スナップと接続の設定(G)で調節。
またグリッドで画面が埋まり、見づらい。右上の[井] アイコンで非表示にする。 |
|
|
|
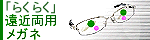 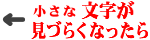 |
|
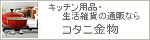 |
|
|
|
|
|
■3■ 画像を貼り付ける |
|
【ポイント】 四角なマーク = ハンドルを表示して、位置・大きさの調節や回転も |
|
Drawgraphic 初期版 への挑戦記録は → こちらをクリック |
|
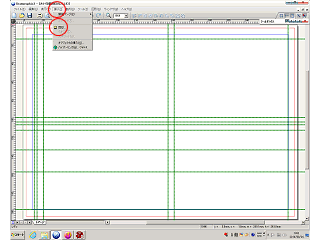 |
|
用紙(ページ)の準備ができたので、「地図」(ペイント系ソフト = 点で描くので、拡大するとギザギザが見える gif データ)を貼り付ける。
左上メニューバーの
挿入 (I)
↓
図 (I)
画像データの保存されたファイルの場所へ移動して、画像データの一覧を表示する。
↓ |
|
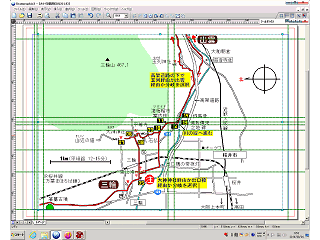 |
|
一覧から挿入する「地図」をクリックすると、画面に挿入される。
「地図」などの画像データはギザギザが目立たないように大きめに描いて縮小して使うようにしている。
大きさを調整(縮小)するには・・・
四隅の■マーク(ハンドル)をマウスでドラッグして縮小する。
四隅以外(上下左右)の■マークに触れると図形がタテヨコに縮んだり伸びたりするので注意。
|
|
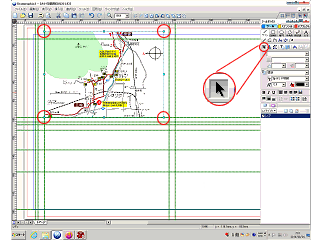 |
|
画像の位置の移動は・・・
画像そのものをクリックし、四隅の■マーク(ハンドル)の付いた状態でドラッグ(*)する。
(*) ズルッと移動した後、離すので、ドラッグ&ドロップとも呼ばれる。
なお、移動したり、縮小したりする際は、ツールボックスから「選択/移動/拡大縮小」機能の[↑] アイコンをONにしておく。
↓ |
|
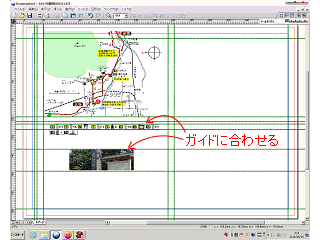 |
|
同じ作業を繰り返して、残りの画像データも貼り付ける。
↓
|
|
|
|
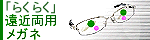 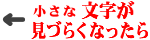 |
|
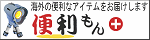 |
|
|
|
|
|
■4■ 文章を入力・編集する |
|
【ポイント】 文字枠の範囲(= 大きさ)は予め設定できずに「後出し」で範囲調整 |
|
Drawgraphic 初期版 への挑戦記録は → こちらをクリック |
|
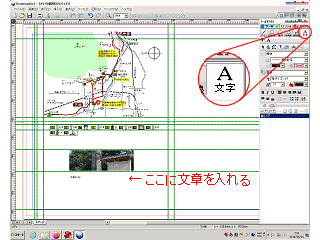 |
|
初期版で最も苦労した(挫折した)文章の入力。
初期版で苦労しているので、DG2 ではスイスイ。文章枠なんて作らない。まず文章を希望する箇所に入れる。
ツールボックスから・・・
[A] = 文字入力アイコン
(テキスト入力)
↓
左上メニューバーの
書式(O)
↓
テキスト(T)
↓
|
|
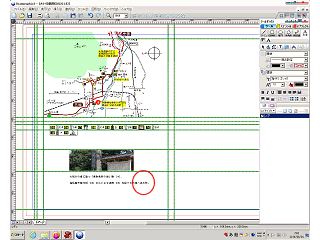 |
|
MSゴシック、サイズ 8.0 を選択
(ツールボックス内も一部連動)
↓
[OK] ボタン
文章はキー入力してもいいが、テキストをコピーしてもいい
↓
クリックした後ろに、指定した字体で文章を入力することができたッ! しかし、写真の左右幅を超えてしまう。
初期版で苦労の結果、この後、ハンドルを表示させて左右幅や位置調節ができることはすでに承知。 |
|
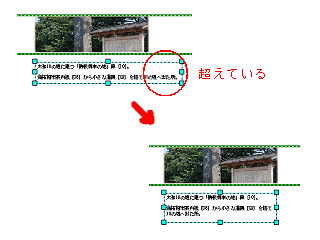 |
|
ツールボックスから・・・
[↑] =選択アイコンをクリック(ON)
↓
文章の上をクリック・・・
画像と同じ8つの■マーク(ハンドル)で文章が囲われる。 左右、上下の■を写真の左右幅と、3行になった文章の高さに合わせてドラッグする。左右は文字数、上下は行数が増減するだけで、画像の■と違って、文字そのものは伸び縮みしない。初期版の時は驚きの発見だったが、もう慣れてしまった。
「枠」の「後出し」だが・・・マ、いいや。
ツールボックスから・・・
[T] = テキスト編集アイコンでクリックするかダブルクリックで「 I 」型のカーソル(キャレット = 挿入記号と呼ぶ)を出せば、文章の書き換えもできる。 |
|
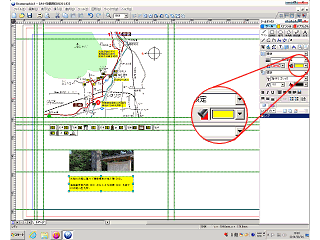 |
|
横道にそれるが、ツールボックスのスタイル設定から「イエロー塗り」を選択すると、左画面のように文章部分の背景がイエローに変わる。
なるほど・・・文字は「色のない図形上」に配置されているので色をつければこうなるわけだ。写真の上なら「ホワイト」がいいだろう。
この作例では下の2行だけを強調するため黄四角の背景をつける。文章を2段にわけてもいいが、練習のために、ここでは背景をつけず、後で下の2行の後ろに黄色の四角形を描いてみよう。 |
|
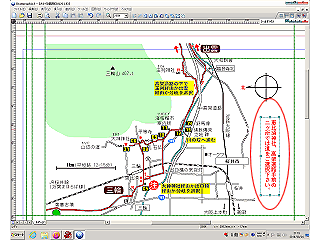 |
|
次に、縦書きの文章入力を確認。
ツールボックスから・・・
[A] = 文字入力アイコン
↓
メニューバーから、書式(O)
↓
テキスト(T)
↓
文字・・・色=レッド
テキストブロック・・・縦書き
↓
[OK] ボタン
この後、文章を入力したのが左画面。 |
|
|
|
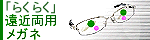 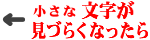 |
|
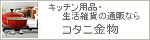 |
|
|
|
|
|
■5■ 罫線・枠線を描く |
|
【ポイント】 文字部分を囲う枠線は「線塗りスタイル」で色を選択 |
|
Drawgraphic 初期版 への挑戦記録は → こちらをクリック |
|
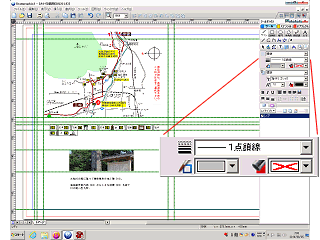 |
|
用紙のほぼ中央の縦のガイドに沿ってグレーの1点鎖線を引く。
印刷したマップの「山折り」の目印になる。
操作方法は初期版と変わっている。
ツールボックスから・・・
線種設定窓で「1点鎖線」を選択
↓
下の線色「グレー」を選択 |
|
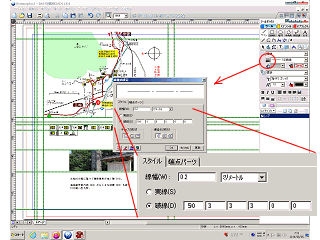 |
|
線種設定窓の左にあるアイコンをクリック
↓
線種の設定ウインドゥが開く
↓
スタイルタブの
線幅=0.2 ミリメートル
破線=50-3-3-3-0-0
と設定した例(破線の数字は1/2がmm寸法になるようで、約30mmごとに点が入る1点鎖線ができた) |
|
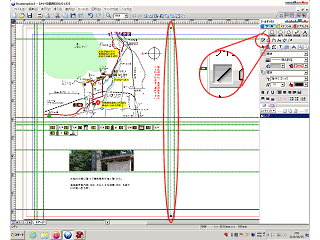 |
|
ガイドに沿って罫線を引くのでガイドが動かないよう「ロック」を確認し、
ツールボックスから・・・
[/] = 直線アイコンをクリック
(ラインアイコンと間違えないように)
↓
ガイドの横に線をひく。[Sift] キーを押しながら、マウスでタテに線をひくと傾かない
線がガイドと重なり、しかも色がグレーで見にくいので、少し横にひいておいて、確認後に移動することにした。 |
|
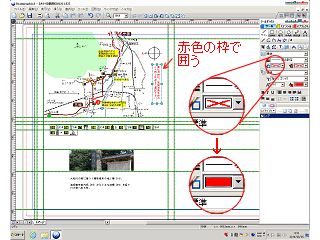 |
|
次に、赤文字の縦書き部分は注意事項なので、赤枠で囲って強調する。
ツールボックスから・・・
[□] = 四角形アイコンをクリック
↓
線色=[レッド]
面色=[×]
↓
線種設定窓で「標準」を選択
↓
縦書き部分をクリックして囲う
(線幅0.5mmの赤い実線の枠)
|
|
|
|
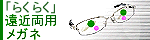 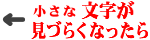 |
|
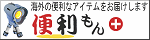 |
|
|
|
|
|
■6■ 前後関係を調整する |
|
【ポイント】 DTP ソフトの基本機能のひとつで、アイコンボタンで簡単 |
|
Drawgraphic 初期版 への挑戦記録は → こちらをクリック |
|
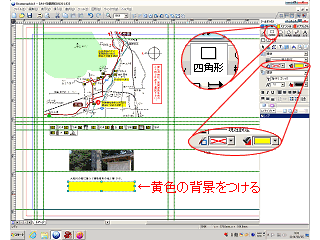 |
|
練習用に残しておいた、説明文章の下2行への黄色の背景付けは…
ツールボックスから・・・
[□] = 四角形アイコンをクリック
↓
線色=[×]
面色=[イエロー]
↓
マウスで文章の下2行を四角に囲う |
|
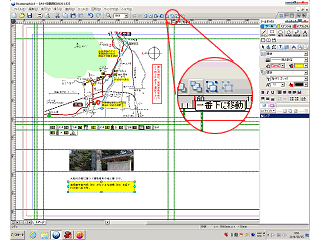 |
|
文字の上に黄色の四角が重なってしまったので、前後関係を変える。
■マーク(ハンドル)で囲ったまま
ツールバーの「一番下に」アイコンをクリック
図形(D)から「最背面へ移動」を選択しても同じ結果になる。
切り取った四角な色紙と透明フィルムに印字した文章の2枚を前後を考えながらノリ貼りする要領だ。 |
|
|
|
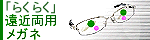 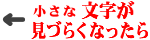 |
|
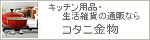 |
|
|
|
以下 初期版Drawgraphic と同様の操作は省略。
|
|
■7■ ページ数の非表示…初期版参照 |
|
【ポイント】 1枚モノのチラシにも「1」が入る |
|
Drawgraphic 初期版 への挑戦記録は → こちらをクリック |
|
|
|
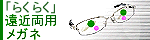 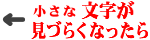 |
|
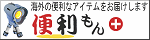 |
|
|
|
|
|
■8■ 文字間・行間の調整、文字修飾…初期版参照 |
|
【ポイント】 反転した部分 だけに文字間・行間、文字修飾が反映される |
|
Drawgraphic 初期版 への挑戦記録は → こちらをクリック |
|
|
|
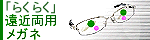 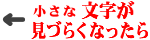 |
|
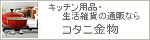 |
|
|
|
|
|
■9■ ページの追加(改良=ガイドもコピーできる) |
|
【ポイント】 挿入(I) →新規ページ(P) →追加(A)(B)(T) するとガイドが消えたが… |
|
以下の操作はデータかモードによっては機能せず再検証中です。
(データが大きい (?) 場合など、下記の貼り付けができなくなる事例があります。)
Drawgraphic 初期版 への挑戦記録は → こちらをクリック |
|
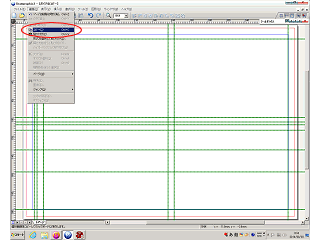 |
|
ガイドの入ったページを用意する。
(文章や画像が入っていてもいいが、それらもガイドと共に新しいページにコピーされる。文章や画像の一部を利用する場合は、共にコピーした後、不要な文章や画像を削除するといい。)
メニューバーから・・・
編集(E)
↓
コピー(C)
(コピー(C)がグレー色で利用できない場合は先にツールボックスの選択アイコン[↑] をクリックしページ上をクリックすると、黒色表示になる。)
↓ |
|
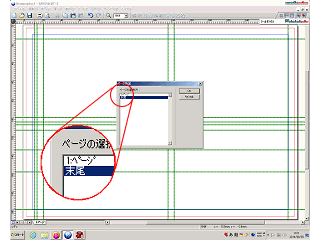 |
|
コピー(C)の後、メニューバーから・・・
編集(E)
↓
貼り付け(P)
↓
ページの選択窓から「末尾」など
ページの追加場所を選択
↓
[OK] ボタン
(ページの選択窓が表示されず、貼り付けを利用できない事例がある)
|
|
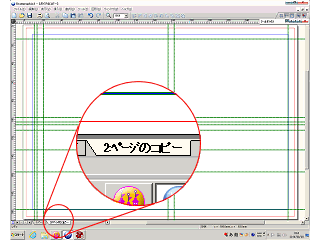 |
|
ガイド付きの新しいページが末尾に追加された。ページ名が「2:ページのコピー」となるのは妙だが、ページ名は変更できるので、この際、無視。
ページ名の変更は・・・
ページ名を右クリック
↓
プロパティ
↓
ページ名を書き換える(1:,2:,3: のページ数が自動的に頭に付く)
とにかく、ガイド(ライン)がコピーできることは(当たり前の機能だが)感動的な改良(注)だ!
(注) = この操作手順が初期版でも有効だったか否か、プログラム削除後の今となっては検証できない。
|
|
|
|
【統一レイアウト】 この作例のように、各ページがすべてほぼ同じレイアウトの場合は以上の操作でページを追加すると、各ページの同じ位置にガイドがコピーされるので便利。
(後でどこかのページのガイド位置を変更しても他のページのガイド位置は変わらない点、注意)
【個別レイアウト】 チラシの表・裏のように、各ページでレイアウトが異なる場合は従来通り、挿入→新規ページでページを追加するといいだろう。追加したページにガイドが必要なら1本づつ新設する。
|
|
|
|
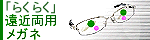 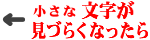 |
|
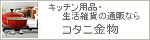 |
|
|
|
|
|
■10■ 伝票・ラベル・名刺用紙へ印字…初期版参照 |
|
【ポイント】 DTP の機能とは言えないが、重宝している「小ワザ」の利用方法 |
|
Drawgraphic 初期版 への挑戦記録は → こちらをクリック |
|
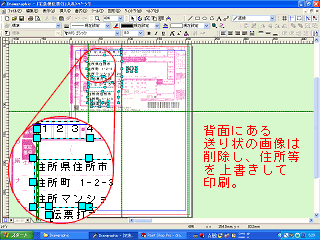 |
|
■運送便の送り状の住所など■
(左は、Drawgraphic初期版での作例) |
|
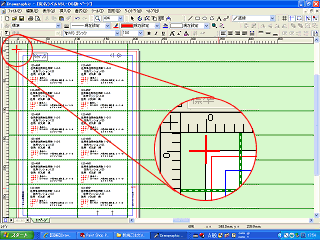 |
|
■ラベル用紙■
(左は、Drawgraphic初期版での作例) |
|
|
|
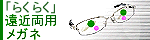 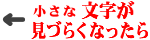 |
|
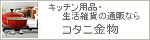 |
|
|
|
|
|
■11■ その他の作例(印刷用版下原稿・案内状)…初期版参照 |
|
【ポイント】 作例 1、2の他に「こんなことも」できることをご紹介 |
|
Drawgraphic 初期版 への挑戦記録は → こちらをクリック |
|
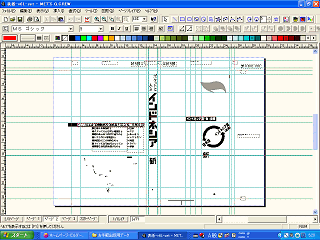 |
|
■印刷用版下原稿■
(左は、G.CREW での作例) |
|
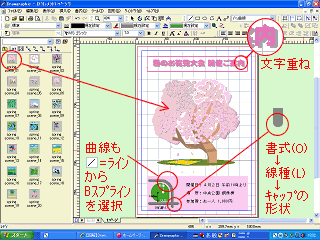 |
|
■案 内 状■
(左は、Drawgraphic初期版での作例)
|
|
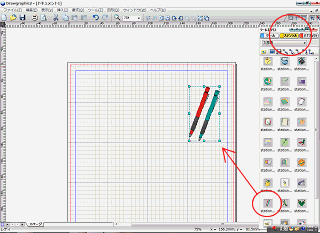 |
|
【初期版とDG2との違い】
案内状などで既製のイラスト類を利用する時、DG2では
ツールボックスから・・・
ステンシル(図柄版)をクリック
↓
下の窓から、文房具(例)を選択
↓
利用する文房具のイラストをクリックして、ページ上にドラッグ&ドロップ
↓
位置や大きさをマウスで調整
|
|
|
|
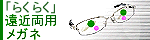 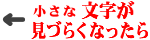 |
|
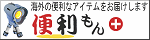 |
|
|
|
(以上、ご感想は下のメールでどうぞ。)
|